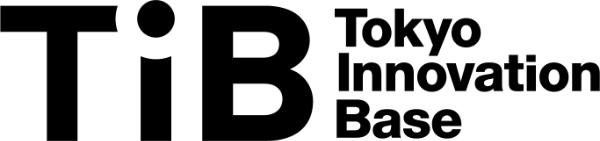JP/EN
未来を切り拓くスタートアップへのメッセージ
オードリー・タンさん
AIをはじめとする情報技術の進化は、私たちの暮らしや社会、都市の姿を大きく変えていく。こうした変革を牽引していくのは、先進的な技術や新たな発想を持つスタートアップだ。
2024年11月27日、Tokyo Innovation Baseで「TIBプレミアム・メンタリング」が行われた。これは、第一線で活躍する先輩起業家や経営者から、将来有望なスタートアップにメンタリングの機会を提供する取組だ。そのキックオフセッションで、最初のメンターとなったオードリー・タン氏は、集まった多くの起業家や学生たちに対して、台湾でのAI活用の成功事例を交えながら、スタートアップに期待される役割について語った。

AIは、共感と対話を生み出す鍵だ
16歳でIT企業を共同設立して成功し、35歳で台湾史上最年少の閣僚(デジタル発展相)に任命された経験を持つオードリー氏は、多様性と共存を意味する「プルラリティ」の重要性を強調し、「AIはただのツールではなく、共感と対話を生み出す鍵だ」と語った。
2014年当時、台湾政府の支持率はわずか9%まで低迷し、市民と政府との間には深い不信感が生まれていた。政府が何を発表しても、2000万人の市民は全て反対する、とまで言われる有り様だったというのだ。
そうした中で、台湾では、市民が自由に意見を発信し、合意形成を目指すためのオンラインプラットフォーム(vTaiwan)が導入された。このシステムでは、設定された議題について、市民が意見を投稿し、その意見に対して賛成・反対などを表明する。AIが多様な意見をグループ分けし、議題に対する懸念や重視する点などが可視化される。そして、対立する立場の者が双方納得するような意見に注目が集まる仕組みとすることで、分断ではなく合意形成に導く効果がある。このシステムによる議論を政策に反映させることで、政府と市民の間の溝が埋まり、台湾政府の信頼回復に寄与したという。

ライドシェア導入の合意形成やオンライン詐欺対策にも効果
オードリー氏は、社会課題の解決に挑むスタートアップにとっても、多様な価値観を尊重し、共感を生む仕組みを設計することが、重要なアプローチであると訴える。台湾におけるUber(ライドシェア)の市場参入を一例として挙げた。台湾政府はUberとタクシー業界が共存できるように、既存のタクシードライバーへの影響の軽減と過疎地域でのライドシェアによる交通手段確保という双方の意見を両立する方策を探った。この際、オードリー氏のシステムを活用して、「なぜUber導入に反対するのか」という点に着目して、市民の意見を整理し、ステークホルダーによる対話を進めたことで、当事者の懸念をクリアし、Uber導入を合法化に向けた合意形成が可能になったという。
さらに、台湾政府は詐欺対策にも成功した。システムにより20万の市民にショートメッセージを送り、ディープフェイクやオンライン詐欺に関する議論に参加するよう呼びかけたことが効果的であったようだ。デジタル署名など、インターネット上の規制等に柔軟に応じることで、台湾においてはソーシャルメディアによる詐欺が90%も減少したという。
このように、AI技術を活用できれば、より良い結果を生む。「多様な見解や価値観を集約できる情報技術を導入することは、一人の政治家のみによる政策立案より優れている」とオードリー氏は述べた。
そして、オードリー氏は、次のメッセージを参加者に伝えた。「Internet of Things」(モノがつながる)から「Internet of Beings」(人がつながる)へ、「virtual reality」(仮想現実)から「shared reality」(共有現実)へ、「User experience」(ユーザー体験)から「Human experience」(人間体験)へ、「machine learning」(機械学習)から「collaborative learning」(協調学習)へマインドチェンジしよう。そして、「singularity」(技術革新による劇的変化)を意識しながら、「Plurality」(多様な意見の共存と協働)を大切にしよう。

コミュニティが主導するイノベーション
キックオフセッションの後半では、Sakana AIの共同創業者 COOである伊藤錬氏とオードリー氏が対談した。Sakana AIは、東京発のスタートアップであり、開発に莫大なコストをかけない新たなアプローチで、わずか1年でユニコーンへと成長を遂げた注目企業だ。Sakana AIは、オープンソースの数十億の言語モデルを組み合わせることにより、GPT-3.5相当のモデルを起業3か月で開発し、かかった費用はわずか24米ドルだったという。
伊藤氏は「コミュニティが主導するイノベーションというオードリー氏の考えに賛同している」と言う。2人は、アジアの文化や地域特性に根差したAIエコシステムの開発の必要性について語り合った。「画一的なものでなく、各地域の固有の文化が反映され、多様なニーズに対応できる独自のAIエコシステムを開発することが重要だ」というオードリー氏。こうした考えは、AIやデジタルテクノロジーの分野での活躍を目指すスタートアップにとって重要なヒントになるだろう。

優秀な人材をどうやって引き付けるか
キックオフセッションの最後には、参加者から多くの質問が寄せられた。「優秀な人材をどのように引きつけるか」というスタートアップからの質問に対しては、伊藤氏が「ビジョンを共有し、意義のある挑戦を提示することが重要だ。オープンソースの開発と社会の課題解決という我々のコミットメントは、ともに働きたいという多くの人々から共感を得られている」とコメント。さらに、オードリー氏は「起業を経験したシニア世代にも素晴らしい人材が多く存在する。彼らは自分の仕事がどのように社会に貢献しているか実感できることを重視する」と付け加えた。
また、「国際的なメンバーで構成されるチームを上手く運営するにはどうすればよいか」という学生からの質問に対して、オードリー氏は時差のある各国の開発メンバーでのチームビルディングを行った経験に触れながら、「経験を共有することを重視した。ウェブ会議を開くときにも、例えば、同じビールを飲みながらやるとか、距離を超えてリアリティを共有する工夫が大切」と語った。伊藤氏もこの意見に賛同し、「お互いを理解するために、トライアル&エラーを続けていくことだ」と話した。

AIの次なる進化、スタートアップによる挑戦への期待
両氏は、AI技術の次なる進化について「エージェント・ベース・モデル」(個人や組織の相互作用をシミュレーションするためのコンピュータモデル)や「コミュニティ・アライメント」(コミュニティの連携・協働)の導入が鍵を握ると考える。「文化的な価値や地域の要望をAIに実装させることが求められる」というオードリー氏。伊藤氏は、「AI開発は始まったばかり。既存技術を超えて、持続可能なエコシステムを構築したい。医療制度、学校教育、物流、選挙制度、治安維持など、よりよい社会の実現に直結している」とし、参加者らを鼓舞した。
最後にオードリー氏は、「オープンイノベーションとオープンソースの力で、未来への基盤を築きましょう。私たちが『良き祖先』として、次世代に持続可能な社会を引き継げるよう、スタートアップの挑戦に期待しています。」と締めくくった。