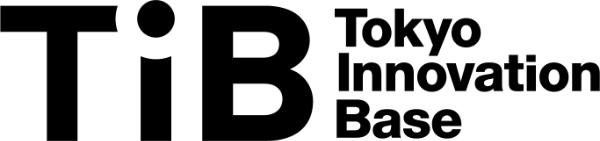ポジティブに粘り強く、ジェットコースターのような毎日を楽しんでいく。
ウォンテッドリー株式会社 代表取締役CEO 仲暁子氏
今回のTIBプレミアムメンタリングのメンターは、ウォンテッドリー株式会社の代表取締役CEO仲暁子さん。公募で選ばれたメンティーは、「物語を通じて会話が可能なエンタメ体験を提供」しているOselAI株式会社の本間さんと、「生成AIの力で業務効率化と生産性向上のサポート」している株式会社EggAIの中島さん。

メンティー2社が自社の活動をプレゼンし、悩みを直接質問する形式で進められた。ビジネスSNS「Wantedly」を通じて、人と人が繋がることにより、個人の可能性を最大限広げるサービス作りに取り組んでいる仲さんは、「失敗しても挫けず、どんどん新しい挑戦を続けていくこと」と「直感的な成長のチャンスを逃さないこと」の大切さを伝えていた。

プレミアムメンタリング後のインタビューでは、メンタリティの大切さや、チームビルディングで得た気づきなどについて語ってくれた。
「時間の切り売りはしない」のメンタリティで生きる
ウォンテッドリーの今の広がりを見ると、起業当初からスケール化を目指して綿密な計画を立てていたのでは?と考えてしまうが、仲さんに起業のきっかけをたずねると意外にも「自分が何か作ったもので社会にインパクトを与えられたら!という思いは強かったのですが、最初から大きくスケールさせたいというわけではなかったです」との答え。ビジネスとして大きな野望を描いていたというよりは、サービスを作って、収益につながって、それで生活していけたらいいよね、という感覚だったという。

そこには仲さんの原点がビジネスパーソンというよりは、ものづくりの作り手だったことが影響しているのかもしれない。
「子どもの頃から家にパソコンがあり、ホームページやコミュニティサイトを作ったり、ショート映画を作ってみたりとか色々していました」。
自分が作るものでインパクトを与えられた時の確かな手触り。一方で、学生時代に体験した単純作業の単発バイトでは、終業時刻の5時に早く近づけと時計ばかりを見る体験をした。「すごく辛くて。早く1日が終わってほしいと思うんですけど、それって早く死にたいと思っているのと同じで、結構な自己矛盾じゃないですか」。
その頃から心に刻まれたのが「時間の切り売りはしない」というメンタリティで生きること。焦りに近いその衝動が、起業にも生きた。
“当たり”は確率論――失敗が生んだPMF(Product Market Fit)
実際に起業をする前から、これが「当たる!」と確信を持てる起業家は少ない。仲さんも当時、PMFするまではピボットを繰り返した経験をしているという。
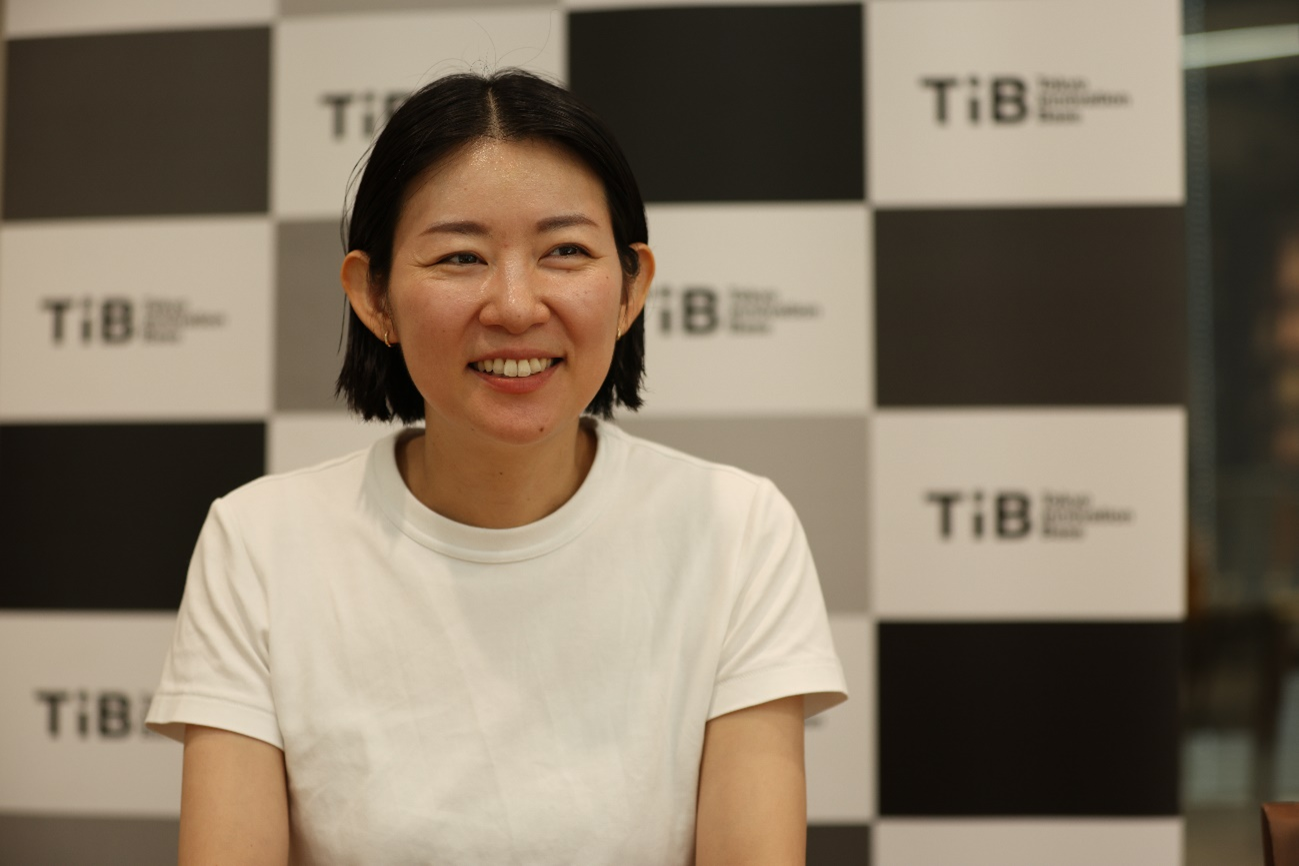
「成功は確率論のようなもので、GoogleやYouTube、Facebookも最初から当たったわけではありません。仮説検証を繰り返す中でやっと当たるというプロセスをいかに高速で回せたか、ということに尽きると思います。狙ってやるという人もいるかもしれませんが、私はそういうタイプではありませんでした」
そう聞くと、ウォンテッドリーが“当たった”のはなぜなのか、やっぱり知りたくなってしまう。そもそもto C系は消費者の行動が読みづらく、変化も激しいため、予測が難しい。ただ難しいけど、やはり重要なのは“顧客のペインやニーズへの気づき”だという。

「あの当時、私も若かったので、ユーザーと同じようなマインドや課題を持っており、こういうのが欲しいというのが、ややシャープにプロダクトに反映されたということはあるかもしれません」と仲さんは分析する。
ウォンテッドリーのサービスは、時給や待遇ではなく、共感やビジョンなどをベースにマッチングするビジネスSNS。そうした形にしたのは、自分がそういうサービスが欲しかったからだという。
「アルバイト雑誌で、時給や場所が載っていても結局何をやるのか人の顔が見えなくてわからないな、というのがあって、実際にその会社がどういう人がいて、どういう思いでやっているのかわかった方が良いなと思って、それを作りました。そういう意味では、自分が抱えている課題を解決したら“当たった”みたいなことは言えるのかも」

では、“当たった”感覚は自分でわかるものなのか?起業に取り組んでいる人なら誰もが気になるところだ。
「PMFしたら、本当に数字の伸びが変わります。ユーザー側だと、リファラルとかオーガニック(自然流入)で入ってくるユーザー数が、角度がギュって変わるのですごく上がったってわかりますし、ビジネス側で行くと、インバウンドから入ってくる客数とか、商談からの成約率が変わったりします」
真のPMFというのは、とにかくニーズがたくさんあって、向こうからどんどん連絡がきて使わせて欲しいと言われるような状況だという。「なので当たったら、データで絶対わかります」と仲さん。フェーズが変わっていく状況を身をもって体験した起業家ならではの感覚が伝わってくる。
友達と仕事は別物――チームビルディングで得た気づき
サービスとしては、粘り強さとプロダクトの質で成長を実現した仲さんだったが、創業初期の苦労は別のところにも潜んでいた。それはチームビルディング。
まだ、利益が出ていない小さな会社だとしても、大海原に漕ぎ出すには船に仲間を乗せる必要がある。一体誰を選べばよいのか———?多くの起業家が悩むところでもある。

仲さんの最初の失敗は、会社で友人を採用してしまったことだという。友人が上司と部下という立場に様変わりし、友情が壊れてしまったり、うまくいかなくなったり……。
「組織が不安定になる時期が何回かあると思うんですが、私の場合は創業初期にそれが起こりました。友人を面接などをしないまま『とりあえず入ろうよ!』と誘ったのですが、仲が良くて楽しい時間と、成果を出すために根を詰めてやる時間は全く別物でした。それがよくわかっていなかったですね」

結果として現在は、優秀な人材が集まっているというが、それは「プロダクトへの共感」「会社の成長から将来性を信じて」やってきてくれるのだという。
優秀な人材はすでに安定的な生活を手にしている場合も多い。それを捨てて来てもらうためには、給与だけでなくストックオプションや、将来的なリターンを提示するなど合理的な判断があってよいというアドバイスも。また初期の人が少ない時期は、専門性を分け、自分ができないことを補完できる人を採用するといった知見も語ってくれた。
しかし何を置いても、採用で最も大事なのは「入社後の期待値を調整すること」と指摘する。

「入社後に何を求められるかということを、相手もわかっている必要があるし、明確に伝える必要があります。『こんな大変だと思っていなかった!』というのがきっと出てくるので、大変なことも正直に共有することが不可欠です」
創業期の大変さを乗り切った仲さんだが、それを支えた重要な起業家としての資質は何かと問うと、「私は楽観性だと思います」ときっぱり答えた。起業を「ジェットコースターのような生活」と描写するが、一度寝ると落ち込んだことを忘れられる特性を持っていたからこそ、夜も寝られなくなるような心配事を乗り越えられたという。
「起業するとツライことがいろいろあるんですけれど、私は割と復活するんですよね。レジリエンスと言ったりするんですが、くよくよしていても『なんとかなりそう』って思えるので、意外と私って楽観的なんだなと思いました」と笑う。

また、もう一つ、重要な資質として「粘り強くやり続けること」をあげた。起業はうまくいかないことの連続。諦めずに続けられるかが問われるのだという。
高い目標が原動力に
結果を出す企業は、どんな目標設定をしてきたのか。そんな質問を仲さんにぶつけてみた。そもそも目標設定はしていたのかと聞くと、「めちゃくちゃしていました(笑)」と仲さん。

「上場前は常にアッパーな目標を設定していたので、毎回・毎回、“未達”で辛かったですが、すごい勢いで引っ張っていった原動力になったと感じます」
組織運営にとって目標設定はトップスリーに入るくらい大切な要素と断言する仲さん。目標設定と評価のサイクルは非常に重要な要素であり、個人が成長を実感し、長く会社で活躍する、そしてそれが会社の成長につながるというサイクルを構築するために不可欠とのこと。
最後に、起業を目指す若者たちへのメッセージをお願いすると、仲氏は「Just do it(とにかくやってみること)」かな?とさらりと答えた。ポジティブに、粘り強く、これだと直感したことを高速に検証していく。起業家にとって重要なことを端的に示した言葉を送ってくれた。